苗 代 (H23.6.24)
モミ準備(1)
1.昨年、稲刈りをした後、種モミ用として、乾燥機に入れないで、ムシロに、広く並べて自然乾燥する。
・1反25枚の計算で、
25枚分×1.5合×1.4(40%の分増し)=5.25升
また、水洗い・軽いモミの除去及び、種まき時のロスを考えて、
40%の分増し
モミ準備(2) <苗代5日前>

2−1 水洗い
モミ種を大きな容器に入れ、モミを水洗いして、水に、馴染ませる。
2−2 塩水で選別
ばか苗病、いもち病、もみ枯細菌病に、罹っているモミを減らし、
発芽不良のモミを取り除くため、
・食塩濃度
水20Lに、食塩4.1kgを入れて、よく混ぜる。(比重1.13)
<作業>
食塩水の入った容器に、水洗いしたモミを入れ、浮いたモミを捨てて、
沈んだモミを取り出す。
2−3 水洗い
塩分を取り除くため、よく水洗いをします。その後、水を切ります。
2−4 薬液調合・消毒
・テクリードCフロアブル(200倍希釈)
ばか苗病、いもち病、ごま葉枯病に加えて、細菌病である、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病、褐条病に有効な
稲の総合種子消毒剤
・スミチオン乳剤 (1000倍希釈)
イネシンガレセンチュウを、防ぐ
・調合の仕方
モミ種と同体積量の希釈液を作る。
モミ種10kgで、水20Lに、テクリードCフロアブル100mlとスミチオン乳剤20mlを加え、混ぜる。
<作業>
調合液にモミ種を入れ、24時間浸す。(冷たい時は、少し温める)
途中で、1〜2回、かき混ぜる。
2−5 風乾
24時間薬剤に浸漬したモミを、水洗いしないで、取り出し、ムシロを広げ、自然に、乾かす。
2−6 浸種
3日ほど水に浸ける。
(100=25℃×4日)または(100=33℃×3日)になるように
床準備(3)
3−1 トラクターで耕す
草が生えてない程度に、10日前には、前もって、トラクターで耕しておく。
3−2 仕切

・苗代する面積を計算して、仕切の畦を作る。
苗代する場所の境に、波板を入れ、
土で倒されないようにする。
・水をいれて、トラクターで耕し、
ドロドロの床土して、1日放置。
床準備(4)
 4−1 枚数分の寸法を測り、田に印を付け、 4−1 枚数分の寸法を測り、田に印を付け、
ロスの無いようにする。
4ー2 チョ縄を張り、土をあげる。(そこが溝になる)
4−5 板でならし、水面が均等になるように調整する。
(均等でないと、芽が均等にあがらない)
苗代土(5)
 昨年は、芽の上がりが悪かった。 昨年は、芽の上がりが悪かった。
被せる土も雑菌が培養したもかもしれないので、
今回は、ホームセンターで土を購入。
(農協では、肥料付きの土の粒子が細かい
土が販売されてない。)
そして、通しで篩過作業。
苗代当日(6)
6−1 苗代の機械を置く。
6−2 苗箱にマットを入れる

今年は、規定通りマットに液肥を含んだ水を
ジョロで浸す。(10枚/20L)

6−3 モミと土を機械に投入。
その後、機械を廻し、苗箱で1.4合の
モミと土を載せる。
「モミ」の量を調整する(1枚当たり1合2〜5石)
少量の調整は、プーリーの調整で、
多い時の調整は、板を上下移動する(ネジを回す)
少し、ハンドルを回して、モミの出る量が
落ち着いてから、箱に紙をあて、測定する。
モミの量が少ないと、田植えの時、歯抜けになるし、
多いと、籾がたくさん入り、芽の出が悪い。
土の量を調整(1枚当たり800g)
土が多いと、芽の出が悪い
少ないと、水が多くなったとき、籾が移動して偏り、均等で無くなる。
6−4 昨日均した田圃に、ビィニールシートを引き、上記の苗を並べる。
6−5 昨日、均した苗床に、チョ縄を張り、真っ直ぐ、且つ、苗箱を水面に均一になる様に置く。
6−6 少し置くと、水が浸み上がってくる。土が少ないと、モミが浮き上がるので、そこに土をまく。
6−7 トンネルの枠線を立てる
6−8 寒冷遮またはシルバーシートを掛ける。
6−9 少し水を入れ、一杯苗箱が浸かるようにする。
6−10 水のレベルを自動調整するため、出口の排水土を決める。
<注意点>
シルバーシートを外すた後、水のレベルをあげる。
 苗の上部が枯れたようになっている。 苗の上部が枯れたようになっている。
また、肥料切れか、精気がない。
シルバーシートを外した後に、
水のレベルが低く、水の吸い上げが悪い時に
強い風に煽られると、苗の先が枯れる。
対策として、
シルバーシートを外した後は、
たっぷり水を張る。寒冷紗を掛ければベスト。
  
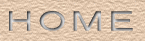
|