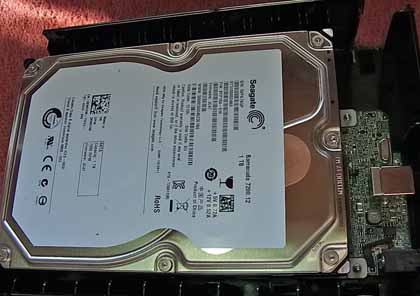|
奈良は、ちょうど1400年前の西暦611年に推古天皇が宇陀地方で薬狩りをしたという記録が日本書紀にあり、
日本における「薬発祥の地」と言える。
これらの流れから<草根木皮>を用いた生薬が広く一般の方々に施薬されてきたが、
これらは、奈良が優秀な薬草の自生地であったことの証とも言え、奈良の薬草が「大和もの」と呼ばれて
珍重されてきた流れがある。
一方、甘粛省(かんしゅくしょう)においても、薬草栽培は主要な産業の一つとして位置付けられており、
当帰(トウキ)、党参(トウジン)、黄?(オウギ)、甘草、大黄、半夏、貝母(バイモ)等、多くの優良な生薬を生産している。
このような中で、薬草の歴史、薬草の功績、薬草を未来に繋げるための方策などについて、
日中の関係者が一堂に会してシンポジウムを行い議論する。 以上、漢方薬日中シンポジウムHPより
1.特別講演「奈良のくすり風土記」 日本東洋医学会 元副会長 米田該典氏
2.講演「甘粛本場の生薬資源の利用の現状と問題」 甘粛省中医薬研究院主任薬師 姜華氏
伝統的な中国医学では、どのような薬が使われるのか、治療のために生薬の組み合わせを
どのように評価するか?
生産資源の現状では、中国・甘粛省における具体的な生薬の分類や地域性を紹介
また、優秀な品質の生薬を栽培するための取り組みを紹介
3.講演「甘粛省定西市中医薬産業発展の現状と問題」 定西市中医薬産業発展?公室主任 馬志忠氏
甘粛省の東南に位置する定西市における生薬の品質や生産量について

←
大和当帰(ヤマトトウキ)
セリ科の植物で、代表的な婦人薬
血の道症に使われる。
当帰の由来は、「まさに帰るべし」の意と云われ
妻が夫の元に帰る事を意味している。
日本では、17世紀中頃、大和や山城地方で
野生していた深山当帰(ミヤマトウキ)系のものを
栽培し、当帰として利用し、
今日の大深当帰(オオブカトウキ)となった。
ただ、この当帰は、手間がかかる。

←サフラン
アラビア語で「黄色」を意味する言葉
月経障害・更年期障害・冷え性などの
産婦人科疾患、
不眠を伴う精神神経疾患、湿疹・アトピー性
皮膚炎・ソウ痒感などの皮膚科疾患の
効果がある。
お裾分けがあった。
|